2017.05.01(2025.04.14 更新)
- 2017年
- うなぎ目線で川・海しらべ!
【自然しらべ2017】うなぎ目線で川・海しらべ! とは?

調べる対象:干潟川
自然しらべ2017 うなぎ目線で川・海しらべ!
自然しらべ2017 うなぎ目線で川・海しらべ!の結果がまとまりました。
日本自然保護協会では、1995年から5年ごとに川しらべを実施してきました。過去4回の調査では、川のまわりの自然の様子は全体的に良い方向に進んでいるという結果でした。一方で、その生活史のほとんどを河川で暮らすウナギは絶滅危惧種に指定されるなど、河川の環境が必ずしも良くなっているとはいえない状況もあります。そこで今年は、ウナギ目線で川の環境を調べてみることにしました。
調査期間の2017年5月~10月に、全国でのべ1194人が402か所でしらべて情報をお寄せくださいました。そのようすをお伝えします。
※実施時期:2017年5月1日~9月30日(終了)
自然しらべ2017 うなぎ目線で川・海しらべ!
ニホンウナギがいま、大きく数を減らしています。ウナギがなぜ減っていしまったのか、今年の自然しらべでは、過去4回実施した「川しらべ」のデータも活用しながら、主な生息場所である川や干潟をしらべることで、その原因をさぐっていきます。
うなぎはどんな生きもの?
ニホンウナギ(Anguilla japonica)は、マリアナ諸島近くの海で産卵し、日本や東アジアの川や沿岸で成長する生きもの(専門用語で降河回遊魚)です。環境省レッドリスト 2017 では絶滅危惧 IB類(EN)、国際自然保護連合(IUCN) のレッドリスト*でも絶滅危惧 IB類(EN)に区分されています。
ウナギの減少には、過剰な漁獲、河川や沿岸域等の成育場の環境変化等、複数の要因が関わっていると考えられています。ウナギの生息のためには、川や河口、沿岸域の自然の連続性が確保されることが重要です。自然しらべ2017では、そんな環境がどれだけ残されているか、川と干潟でしらべます。
二ホンウナギは、そのリストの中でⅠB類(EN)に定められていて、「近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの」とされています。
環境省が作ったレッドリスト2017へ掲載されている絶滅危惧種の合計種数は3,690種です(海洋生物レッドリストに掲載された種を含む)。
謎の多いニホンウナギ~
毎年4月~8月頃に産卵して、6か月程度の時間をかけて、東アジア沿岸域にやってきます。数年~数十年かけて40~50cm以上に成長し産卵場所に向かうという一生を送っています。

自然しらべへの参加協力のお願い
なぜ、川をしらべるのでしょう
川に堰がたくさんあるとウナギが遡上できないからです!

国内の研究では堰の高さが40センチを超えると、うなぎの遡上が難しくなることが分かっています(環境省 2017)。大きなダムは当然遡上の障害になります。また、小さな堰が連続することで、ウナギの遡上や成育に大きな影響を与えます。アメリカの研究では、遡上の障害となるダムを撤去することによって河川内のウナギ個体数が増大したと報告されています。(Hitt et al. 2012)
Nathaniel P. Hitt, Sheila Eller, John E. B. Wofford (2012) Dam removal increases American
eel abundance in Distant headwater streams. Transactions
海からやってくるウナギに大切な場所である干潟

ニホンウナギは南の海で産まれて、シラスウナギとなって黒潮に乗って日本の川にやってきます。成長してウナギとなって、産卵のために南の海に戻るまでの間、川を溯上して生育するもののほかに、溯上せずに河口や内湾に留まったり、海と川を何度も行き来するものがいることが研究から分かってきました。そのため、河口や内湾の干潟などの環境も大変重要です。
主催・協賛・協力
| 主催 | 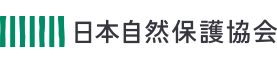 |
|---|---|
| 共催 | |
| 協賛 | |
| 誌面協賛 | |
| 協力 |
|
| 学術協力 | 海部 健三(中央大学法学部 准教授) |
| 川のイラスト | トミタ・イチロー |
| デザイン・イラスト | 君島 晃 |
| イラスト | 荻本 央(よそ見屋 ぷろここ) |
参考
*このページにルビをつけて表示したい方はこちらのサービスなどが便利です。
アダプティブテクノロジー(外部サイト:登録制の無料サービス)
このページをひらがなでよみたいひとは、せんせいやおとうさん・おかあさんに、【こちらのページ】をみてもらってください。




 主な活動 TOP
主な活動 TOP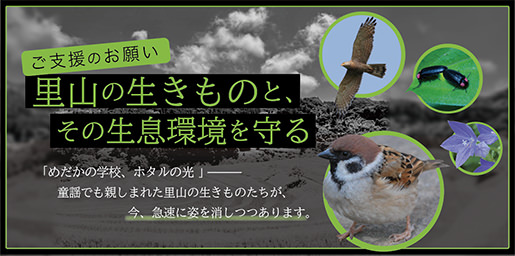
 支援の方法TOP
支援の方法TOP 会員制度/入会申込み
会員制度/入会申込み 遺贈・遺産・お香典のご寄付
遺贈・遺産・お香典のご寄付 チャリボン(本・DVD等での寄付)
チャリボン(本・DVD等での寄付) お宝エイド(不用品の買取寄付)
お宝エイド(不用品の買取寄付) 寄付金控除・褒章制度について
寄付金控除・褒章制度について その他の支援方法
その他の支援方法 講習会日程一覧・お申込み
講習会日程一覧・お申込み





