2018.07.05(2025.01.31 更新)
IUCNレッドリスト-オーストラリアの爬虫類、外来種と気候変動により危機的状況に
読み物
専門度:

左からZ順に、Agarwood (Aquilaria malaccensis) - © Ahmad Fuad、Grassland Earless Dragon (Tympanocryptis pinguicolla)© Will Osborne、Greater Mascarene Flying Fox (Pteropus niger) - © Martin D. Parr、Ironclad Beetle (Tarphius_azoricus) - © Paulo Borges、Rio Pescado Stubfoot Toad (Atelopus balios) - © Centro Jambatu
テーマ:絶滅危惧種
IUCN(世界自然保護連合)が、7月5日にレッドリストの更新を発表しました(日本自然保護協会は、IUCN日本委員会の事務局を務めています)。
IUCN日本委員会とは
IUCNに加盟する国内団体・専門家・事務局の連絡協議のための国内委員会です。1980年に日本において「世界自然保護戦略(World Conservation Strategy)」が発表されたのを機に、IUCNに加盟する国内の団体間の連絡協議を目的として設立されました。2001年10月には、IUCN理事会において正式な国内委員会として承認されました。
スイス2018年7月5日(IUCN発表)
オーストラリア固有の爬虫類類(トカゲやヘビなど)が、外来種や気候変動により深刻な危機に直面しており、オーストラリアに生息する爬虫類の7%が絶滅の危機にあることが、本日発表されたIUCNレッドリストによって明らかになった。
重要な受粉の役割をもつモーリタニアオオコウモリも駆除活動によって、絶滅危惧IB類(EN)にリストされた。かつて絶滅したと思われていた南アメリカの4種の両生類の再発見という良いニュースもある。
IUCNレッドリストは今回の発表によって、93,577種が評価され、そのうち、26,197種が絶滅危惧種に分類されることになった
「今日のIUCNレッドリストの発表は、私たちの地球の生物多様性が直面している膨大な危機を明らかにしました」とインガ―アンダーセンIUCN事務局長は語る。
「外来種、森林火災の変化、サイクロン、人と野生動物の衝突は、私たちの地球の生態系に引き起こされている大災害の理由の一部にすぎません。モーリシャスからオーストラリアまで生物が絶滅に向かって滑り落ちているということは、私たちの文化やアイデンティティが、そして、穀物を実らせるための受粉や健全な土壌の保全に貢献するこれらの種が提供している自然を支える機能が失われるリスクがあるということなのです。」
「国連の生物多様性戦略計画は、絶滅の危機にある種の持続可能な状況に戻すことを各国に求めています。今日のIUCNレッドリストの発表は、絶滅危惧種保全のための緊急の行動が必要であることを示しています。」とジェーンスマート生物多様性保全グループ局長は説明する。
現在、開催されている生物多様性条約の会合でも、絶滅危惧種の保全活動について緊急に行動することを呼びかけている。
オーストラリアの爬虫類が、外来種や気候変動の影響で絶滅の危機に
オーストラリアの爬虫類は、外来種と気候変動の影響によってその危機が高まっており、7%が絶滅の危機にある。IUCNレッドリストの調査で、オーストラリア大陸の爬虫類の包括的な調査の結果、この事実が明らかになった。IUCNレッドリストには、現在、オーストラリアのほぼ全爬虫類にあたる975種が掲載され、その多くは大陸の固有種となっている。
外来種は、絶滅の危機にある爬虫類の半数近くの危機要因となっている。最近の研究によると、外来の野良猫だけで、年間6億匹の爬虫類が殺されていることが分かった。野良猫に捕食されている爬虫類の一つが、グラスランドイヤレスドラゴン(Tympanocryptis pinguicolla)で、絶滅危惧II類(VU)から絶滅危惧IB類(EN)に危機度が上がった。農業管理や伝統的な火入れ、外来雑草などの要因が複合的に影響した森林火災の大きさや頻度の変化が、この種のさらなる危機を高めている。多くのオーストラリアの種と同様、グラスランドイヤレスドラゴンは、ヨーロッパからの定住がはじまる前から、半自然的に起きていた火事にうまく順応していた種である。

▲Grassland Earless Dragon (Tympanocryptis pinguicolla) – © Will Osborne
その他のオーストラリアの爬虫類を危機に追いやる外来種として、1935年にオーストラリアに持ち込まれた有毒のオオヒキガエルがいる。絶滅危惧IA類(CR)に分類されたミッチェルオオトカゲ(Varanus mitchelli)は、オオヒキガエル導入後、捕食したために、ある地域では、97%におよぶ個体数の減少が見られた。同様の毒をもつ固有のカエルや生物がオーストラリアには存在しないためオオヒキガエルの毒に対してとりわけ脆弱になっている。
気候変動もまた、Techmarscincus jigurru(トカゲの仲間 絶滅危惧II類(VU))というクイーンズランド最高峰(バートルフレーレ山)の山頂付近の寒冷な環境に適応した仲間を含む、オーストラリアの爬虫類への危惧を及ぼしている。気温1度の上昇によって、30年以内に、寒冷の環境に適応したこのトカゲの仲間の個体数は50%近く減少するとされている。
「今回のレッドリストの改訂の目玉は、オーストラリアのトカゲ類およびヘビ類の危機的状況である。有毒のオオヒキガエルや飼い猫といった侵略的外来種により危機にさらされていることに加え、侵略的な外来雑草の繁茂や開発行為、火災等による生息地の喪失もしばしばその要因となっている」と IUCNレッドリストコーディネーター(IUCN-SSC Snake and Lizard)の Philip Bowles氏は語っている。
「オーストラリアの在来爬虫類を脅威にさらしているそれぞれの要因を理解することが、政府、地元保全団体、アボリジニー(Aboriginal people)の皆さんの取り組みを効果的なものとすることに役立つだろう。」
他に類を見ないオーストラリアの多様な爬虫類相は、他の場所と独立して進化したものであり、世界全体の爬虫類の種数のおよそ10%を占める。いくつかの種は生態系の構成やより広い食物連鎖において重要な役割を持っている。また先住民族にとって、特に肉食性および果食性のトカゲ類およびニシキヘビは、紋章や伝承、伝統食といった彼らの文化の重要な一部となっている。
アゾレス諸島の昆虫相を脅かす外来植物
ポルトガル領アゾレス諸島の100種を超える昆虫の評価が行われ、74%が絶滅危惧種に分類された。外来植物、土地利用の変化、気候の乾燥化による生息地の急速な劣化が主な要因である。Tarphius属の甲虫で評価された全12種が絶滅の危機にあると考えられる。これらの昆虫は枯れ木やコケ、シダに覆われた環境が必要であるが、ヒマラヤから持ち込まれた植物カヒリジンジャー(Hedychium gardnerianum)が、在来の植物から徐々に置き換わっている。テルセイラ島の甲虫(Tarphius relictus)が特にこの変化に影響を受けており、その生息地が1ha以下に縮小している。この甲虫の評価結果案に基づく、アゾレス政府による保護地域の設立が、この種の一縷の望みをつないでいる。
「昆虫は生態系の重要な要素であり、捕食や受粉といった重要な機能を果たしています」と、Axel Hochkirch氏(IUCNーSSC無脊椎動物保全小委員会の委員長)は語る。
「生息地の小さな変化が、無脊椎動物に大きな影響を与え、島に固有の生物種が特に危機に追いやられています」

▲Ironclad Beetle (Tarphius_azoricus) – © Paulo Borges
モーリシャスオオコウモリが、駆除活動によって絶滅の危機に
インド洋モーリシャス島とリユニオン島にしか見られない大型コウモリである、モーリシャスオオコウモリ(Pteropus niger)は、絶滅危惧Ⅱ類(VU)からIB類(EN)に分類が移った。ライチやマンゴーなどの果物を食べることからコウモリの駆除が政府によって実施されたため、推定個体数が2015年から2016年の間に50%に減少した。
この種は、森林伐採、サイクロン、違法捕獲、電線に引っかかる事故死などの危機要因がある。他の島ではサイクロンによって95%近くの減少が見られたこともあり、サイクロンの数やその強さが増加するとみられていることから、大きな危機要因となっている。
この生物は、固有の植物の受粉を助けたり、種子を拡散させるなどモーリシャス諸島の生態系で重要な役割を果たしている。IUCN種の保存委員会・人と野生動物の衝突に関するタスクフォースでは、モーリシャス政府や、果樹園農家、科学者など他の利害関係者と活動し、ネットの活用や果樹園管理の近代化といった、果物を守る代替手法の模索などの課題解決に取り組んでいる。2015年、IUCNは駆除策によって種の絶滅の危機が近づくことを声明の中で警告した。
一方で、衝突解決の対話を通じて、タスクフォースとIUCN-種の保存委員会コウモリ専門家グループとモーリシャス政府は、関係者が受け入れられる解決策の開発に向けた取り組みを前進させ、2016年以降、駆除活動は行われていない。

▲Greater Mascarene Flying Fox (Pteropus niger) – © Martin D. Parr
両生類の再発見
世界的に両生類は高い危機レベルにあるが、絶滅危惧IA類(近絶滅)または絶滅したと考えられていた4種の両生類がコロンビアとエクアドルで再発見されるという良いニュースもあった。リオペスカドスタップフットトード(Atelopus balios)、クィートスタップフットトード(Atelopus ignescens)、Atelopus nanayは、致死性の高いカエルツボカビ症のせいでいなくなったと考えられていた。カーチアンデストード (Rhaebo colomai)も、生息地影響を受け、永久にいなくなったと思われていた。
「このような再発見は嬉しいニュースであるがこの種は依然人間由来の悪影響を受けている。」とJennifer Luedtke(IUCN-種の保存委員会両生類コーディネーター)は語る。
「これらの種は依然、深刻な生息地の破壊や劣化、外来種による捕食、カエルツボカビ症や気候変動の影響を受け、絶滅から守るために保全状況の緊急的な改善が必要です」

▲Rio Pescado Stubfoot Toad (Atelopus balios) – © Centro Jambatu. CC BY-NC-SA 2.0
日本のミミズが初めて評価された
日本在来のミミズ類43種が、IUCNがトヨタと結んだ協定による資金を利用してレッドリストで評価された。このうち3種は絶滅の危機があるとみなされている(ツリミミズ科和名無し Eisenia anzac, モリオカジュズイミミズ Drawida moriokaensis 、オオフナトジュズイミミズ Drawida ofunatoensis)。集約的農業、都市の拡大、第二次世界大戦ならびに2011年の福島第一原発事故による放射線の影響がこれらの種に対する主な危機である。
ミミズは土壌の空隙や降雨の浸透性を増加させることで健全な土壌の維持を助けている。また多くの食物連鎖の基盤ともなっている。日本では、伝統的に薬や釣りの餌としても利用されてきた。そして文化的な重要性もあり、巨大なミミズが歌を歌い天に昇って竜になったというような神話も残っている。
香料の需要により世界で最も価値のある木の1種が絶滅の危機に
世界でもっとも価値のある木の一種であるマラッカジンコウ(Aquilaria malaccensis) が、伐採と森林破壊によりこの150年で80%以上の個体数が減ったことにより、絶滅危惧Ⅱ類(VU)から絶滅危惧IA類(CR)に再評価された。沈香(じんこう)は、Aquilaria の中心部に侵入してきたカビに対し、防衛機能として木がつくる黒く香ばしい樹脂からつくられる。どの野生の樹木に沈香ができているかを見分けるのは難しく、違法伐採者がこの大切な沈香を見つけるために大量に伐採することにつながった。
マラッカジンコウは香水製造業において、世界で最も好まれる沈香をつくる種のひとつである。

▲Agarwood (Aquilaria malaccensis) – © Ahmad Fuad … CC BY-NC-SA 2.0




 主な活動 TOP
主な活動 TOP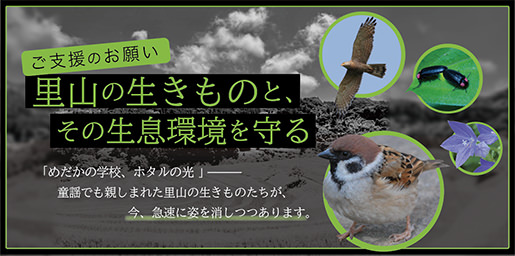
 支援の方法TOP
支援の方法TOP 会員制度/入会申込み
会員制度/入会申込み 遺贈・遺産・お香典のご寄付
遺贈・遺産・お香典のご寄付 チャリボン(本・DVD等での寄付)
チャリボン(本・DVD等での寄付) お宝エイド(不用品の買取寄付)
お宝エイド(不用品の買取寄付) 寄付金控除・褒章制度について
寄付金控除・褒章制度について その他の支援方法
その他の支援方法 講習会日程一覧・お申込み
講習会日程一覧・お申込み






