2018.07.25(2025.04.16 更新)
井の頭自然文化園から能楽師さんに、コサギの羽根を譲渡いただきました。
イベント告知報告
専門度:

▲右:宝生流能楽師 東川光夫さん、左:井の頭自然文化園 コサギ飼育担当の東條 裕子さん
テーマ:生息環境保全絶滅危惧種伝統文化
![]() 事務局長の鶴田です。
事務局長の鶴田です。
2018年7月19日、東京、三鷹市の井の頭自然文化園で、動物園から能楽師さんに、コサギの羽根を譲渡いただきましたので、報告します!
日本自然保護協会の会報『自然保護』2018年1・2月号特集『能の世界と日本の自然』の取材がきっかけで、宝生流能楽師の東川光夫さんより『鷺』という能で使われる道具、鷺冠の羽根が一部失われたままになっていること、江戸時代からの道具を受け継ぐために、羽根の入手についてご相談を受けていました。

▲『鷺』で使用する鷺冠
『鷺』という演目は、人間臭さが出てはいけないので元服前の子どもか還暦過ぎた人間しか演じることができないとされ、頭に「鷺冠」を載せ全身真っ白な装束で舞う神聖なものです。天皇に追われたサギが、天皇の呼びかけに応えて天皇の前に舞い戻ったことから五位の位を与えられたというお話で、これがゴイサギの名前の由来だとも言われています。
宝生流に伝わる鷺冠は江戸時代につくられたもので、体は木製。頭には冠羽を模して本物のサギの羽根が差し込まれていましたが、写真のものは羽根が途中で折れてしまい、残る2つは根元から折れていて修復に困っておられました。
そして今回、伝統芸能の道具ラボさんと多摩動物公園、井の頭自然文化園、当会が協力し、日本の文化と生物とのつながり、生物文化多様性を保全する取り組みとして、井の頭自然文化園で飼育されているコサギの飾り羽の抜け羽根を譲っていただくことになりました。

▲左:伝統芸能の道具ラボ 田村民子さん
その時の様子が当日、NHK首都圏ネットワークで放映されました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180720/k10011541791000.html

▲NHK取材班の前で行われた羽根の譲渡式

▲NHKのインタビューを受ける、井の頭自然文化園の東條裕子さん

▲NHKのインタビューを受ける、宝生流能楽師の東川光夫さん
かつて江戸時代でも街道沿いにあったサギ山は大事に保護されるなど、サギ類は大切に扱われてきました。しかし、戦後まではあったサギ山も高度成長期には小動物の生息できる水辺がどんどん失われ、宅地化されたところや養魚場の付近などから追い払われ、ねぐらや営巣地が減少しています。
今でも大きな川の中州や海沿いの無人島などで集団ねぐらがあり、都心の池や川で採餌する様子もみかける身近な鳥ですが、コサギは鳥獣保護法でも保護され、捕ったり殺したりすることも禁止されています。
現代の能楽師さんは昔のように猟師や鷺山を知る人からサギの羽根を譲ってもらうのは難しく、伝統的な道具の修理に本物の羽根が欲しいと思っても、入手できずにおられました。
そこで、会報の取材をきっかけに伝統芸能と自然保護、動物園のコラボレーションが始まり、多摩動物公園でのイヌワシの保護と羽団扇のイベント「日本の伝統文化のなかに生きる動物たち」やNACS-J市民カレッジでのご講演「能と日本の自然」で生物多様性保全に理解を寄せられ、能楽界から自然とのつながりについて普及啓発に取り組んでいただく実績もある能楽師さんへの譲渡ということで、井の頭自然文化園さんからも快く羽根をお譲りいただけることとなりました。

日本の自然や生き物は文化や歴史の中にも深く息づいているもので、芸能関係者や研究者、私たち自然保護団体が協力してその価値を伝え、継承していくことが必要になっています。今回のようにそれぞれの立場の方々が得意分野を生かして協力し合い、日本の生物多様性、文化多様性をともに守っていく活動を広げていきたいと思います。

担当者から一言
事務局長 鶴田由美子
身近な生き物が意外なところで活躍していること、わたしも今回の譲渡で改めてそのつながりに驚きました。ぜひ自然観察の視点からも能を鑑賞したり、コサギを見たときには能の道具に登場している姿を想い描いてみてください。
【関連する記事】
能の世界と日本の自然
日本の伝統文化のなかに生きる動物たち




 主な活動 TOP
主な活動 TOP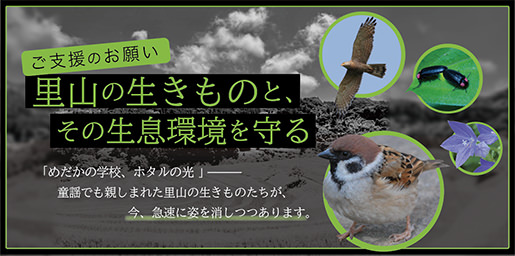
 支援の方法TOP
支援の方法TOP 会員制度/入会申込み
会員制度/入会申込み 遺贈・遺産・お香典のご寄付
遺贈・遺産・お香典のご寄付 チャリボン(本・DVD等での寄付)
チャリボン(本・DVD等での寄付) お宝エイド(不用品の買取寄付)
お宝エイド(不用品の買取寄付) 寄付金控除・褒章制度について
寄付金控除・褒章制度について その他の支援方法
その他の支援方法 講習会日程一覧・お申込み
講習会日程一覧・お申込み






